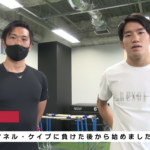こんにちは。健康運動指導士の船倉です。

新型コロナウィルスに伴う、緊急事態宣言解除になり少しずつ日常が戻りつつあります。
しかし、運動施設においてはクラスター発生などの危険が伴うという事もあり制限付きの営業になっている現状にあります。いつまで続くのか・・・?不安は続きますが、止まない雨はありません。必ず不安が解消されるときは来るはずです。
さて、前回の記事で免疫力について少しお話ししました。
運動を継続的に行う事で、免疫力が向上されウィルス感染を予防が出来るという内容です。
では、実際にどのような運動が適しているのか?を解説していきたいと思います。
【ウイルス対策に「運動」は是か非か】
運動はウイルス対策にとって効果的でしょうか?

答えは・・・・
強度により「YES」、
強度により「NO」。
です。
強度というのは簡単に言うと「きつい」「しんどい」か、そうでないかのレベルです。
ウィルス対策に効果的、または逆効果な運動強度は次の通りです↓
・ウイルス対策に効果的な運動強度
→ 「きつくなくて気持ち良い」「きつくなくてスッキリする」→ 低強度の運動
・ウイルス対策に逆効果の運動強度
→ 「きつくて疲労が残る」「きつくて強い筋肉痛が残る」 →中・高強度の運動
【なぜ強度の高い運動が逆効果を生むのか】
先述した「きつくて疲れが溜まる」「きつくて強い筋肉痛が残る」このような運動・筋トレの代償は、
“回復にエネルギーを使う”というところです。
わかりやすい例を挙げると、ご飯を食べてすぐは「眠たい」「ボーッとする」という感覚的現象がありますが、これは食べたものを消化するためには胃や腸といった消化器官にエネルギー(血液)を送り込まないといけないからであり、それ以外の脳や筋肉に送り込まれる血液量が一時的に減少するために身体を休ませようとしている状態です。
人の生理反応として、“何かにエネルギーを使っている時は何かを休ませないといけない”という「意識していなくても起こる自律神経由来の体内反応」があるということです。
疲れた身体や筋肉をはじめとする軟部組織の回復にエネルギーを使っている間は、そうでない時より“免疫に使われるエネルギーの比率が下がってしまう”のです。
また、強度が高い運動や筋トレは、鼻呼吸だけでは追いつかず「口呼吸」にもなりやすいです。鼻には「鼻毛」というフィルターがありますが、口で呼吸をすると喉の粘膜に直接ウイルスが付着していきます。そういった角度からもウイルス対策における中・高強度の運動や筋トレはお勧めしません。
ゆえに、ウイルス対策を考え実行するにあたり「運動や筋トレ」をどう扱うかについては、強い疲労が残る運動・筋トレはしない。強い筋肉痛が残る運動・筋トレはしない。これらを推奨します。個々の持つ体力は違いますので「その人がどう感じている運動・筋トレか」が大切になってきます。
【なぜ強度の低い運動がウイルス対策になるのか】
強度により「YES」だと先述しましたが、効果のある強度とは「低強度」です。
低強度の運動や筋トレはなぜウイルス対策になるのかについて解説します。
現代人は基本的に運動不足です。血流や体液の循環が悪くなっていることが多いでしょう。

運動不足の人が「きつくなくて気持ち良い」「きつくなくてスッキリする」これくらいの低強度の運動であれば、疲労や筋肉痛はほとんど残りません。血液や体液の循環がよくなり、免疫に関わる体内の生理反応の質を上昇させる可能性が高くなります。ゆえにウイルス対策としてもプラスになる可能性を示唆します。
このことから低強度の運動がウイルス対策にプラスになると言えます。
※運動に適さない持病や臨床疾患がないことを前提に。
【実際にどのような運動をすれば良いのか】

低強度が良いと前項に書きましたが、運動や筋トレ種目については具体的に何をすれば良いのでしょうか。
先述したように「きつくて疲れが溜まる」「きつくて強い筋肉痛が残る」ではいけませんので、推奨する種目は「自体重のスクワット」です。
椅子のないところで、椅子に座るときくらいの深さまでしゃがみ、立ち上がる。この繰り返しです。脚の横幅はその人がしゃがみやすい幅でOK。
1日10回を3セットもすれば十分でしょう。身体が少しスッキリするはず。
「ラジオ体操 第一」を1セットするのもちょうど良い強度と言えるでしょう。
そしてこの2つはどちらも家で出来るというメリットがあります。
この時期、リスクは最小限に。
【総 論】
これまでのことから、運動や筋トレは「スッキリする、気持ち良いと感じるくらい」がウイルス対策には適しているといえます。
「疲労困憊、激しい筋肉痛が残る運動や筋トレ」はウイルス対策に推奨できません。免疫力を考えた際に生理学として理にかなっていないからです。
※今回の内容は生理学的知識や見解で解説しています。
著者は医療従事者ではないことを前提とし、「予防的観点」で読了頂ければ幸いです。
健康運動指導士:船倉雅行